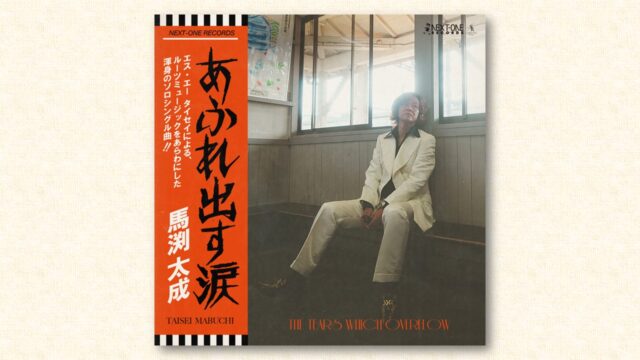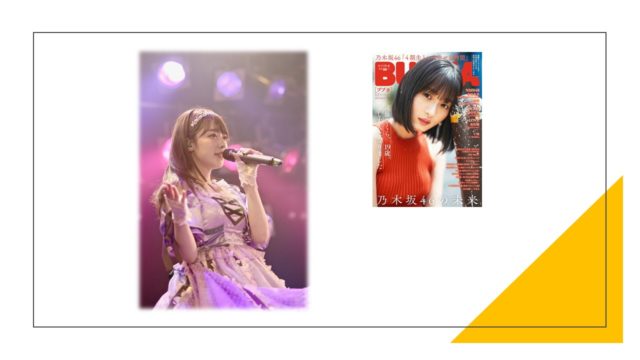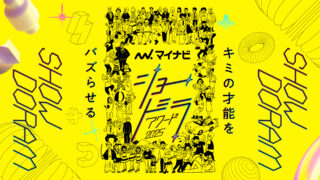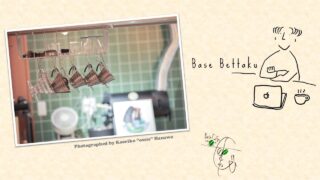音楽家のための法律相談サービス「Law and Theory」水口瑛介弁護士 インタビュー(特集)
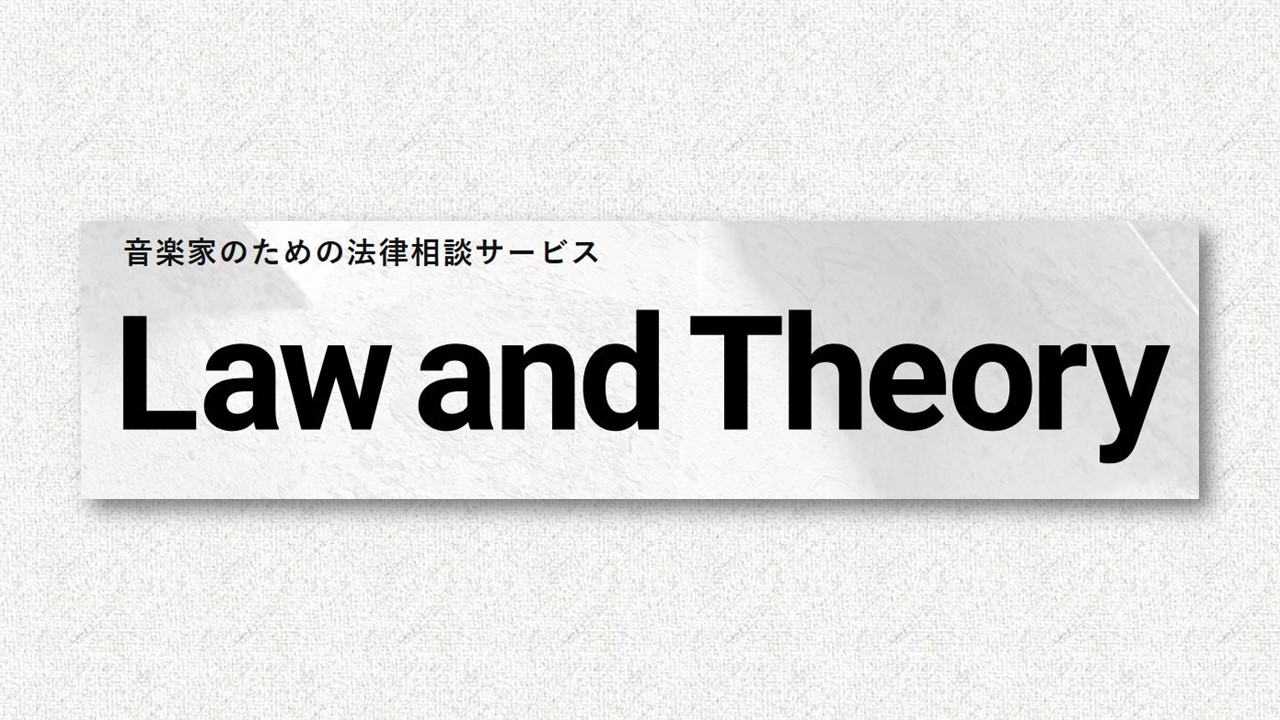
「音楽系フリーランスのための契約ガイド」の研修会が、2025年2月~3月 東京・名古屋・大阪・福岡にて開催されました。今回は この研修会のガイドブックを執筆した、音楽家のための法律相談サービス Law and Theory 及び 同団体メンバーである水口瑛介弁護士のインタビューを特集にてご紹介します。
Contents
音楽系フリーランス
のための契約ガイド
文化庁 主催 / 公益社団法人 著作権情報センター(CRIC) 企画・運営により、令和6年度 文化庁委託事業 芸術家等実務研修会として「音楽系フリーランスのための契約ガイド」が、2025年2月~3月にかけて6回にわたり東京・名古屋・大阪・福岡にて開催されました。
この研修会の第1部では、水口瑛介弁護士 (アーティファクト法律事務所)と清水航弁護士(Field-R法律事務所)による音楽系フリーランス(作家、演奏家、レコーディングエンジニアなど)を幅広く対象とした契約に関する講義が行われました。
また第2部では、レコーディング・ミキシングエンジニアの古賀健一氏、ピアニスト・作編曲家の土屋学氏、作編曲家の山移高寛氏をゲストにトークセッションが行われました。
本研修会の内容は、2025年2月26日にライブ配信で行われた回のアーカイブが公開されているので、そちらにて視聴する事が可能です。
さらに、この研修会の内容をまとめた「音楽系フリーランスのための契約ガイドブック」は、現在 以下リンクからダウンロード可能となっています。
公益社団法人 著作権情報センター(CRIC)Website
音楽系フリーランスのための契約ガイド
https://www.cric.or.jp/archive/index.html
音楽家のための
法律相談サービス
Law and Theory
この「音楽系フリーランスのための契約ガイド」のガイドブックの執筆を務め、研修会にも参加された水口瑛介弁護士 及び 清水航弁護士が、メンバーとして参加しているのが 音楽家のための法律相談サービス Law and Theory です。
Law and Theory Website
https://law-and-theory.com/
Law and Theoryは、音楽と音楽を取り巻くカルチャーをリスペクトする弁護士が、音楽家に無料で法律相談サービスを提供する団体で、2018年1月より活動をスタート。現在は8名の弁護士で運営されています。
参加する弁護士の方々も、過去にミュージシャンとしてステージに立った経験のある方や、現在進行形で演奏をされている方、音楽を心から愛する人々の為、音楽や音楽活動に関する共通言語を使って相談する事が出来ます。
音楽ディストリビューションサービス TuneCore Japan のメディア THE MAGAZINE にて、2020年より連載している「アーティストのための法と理論」の執筆も Law and Theory は手掛けています。
- アーティストのための法と理論 Vol.1 – 楽曲の著作権・Law and Theory for Artists (2020.5.11 THE MAGAZINE )
- 【連載】アーティストのための法と理論 ビギナークラス — エピソード1「楽曲の著作権とコピー」(2022.9.7 THE MAGAZINE )
- アーティストのための法と理論 記事一覧 (THE MAGAZINE)
Law and Theory
水口瑛介弁護士 インタビュー
今回Onigiri Mediaは水口弁護士にインタビューする機会を得たので、活動開始から7年経った現在、Law and Theory に寄せられる相談についてや、団体設立の経緯、また水口弁護士の個人的音楽経験等についても、伺ってみました。
プロフィール
水口 瑛介 / Eisuke Mizuguchi
弁護士(東京弁護士会)
アーティファクト法律事務所代表。音楽、スポーツ、ファッション、インターネットなどのエンターテインメント・クリエイティブ分野や知的財産法を専門とする。
2018年に音楽家のための法律相談サービス Law and Theory を設立。
インタビュー
ーー先ずは「音楽家のための法律相談サービス Law and Theory」を立ち上げたきっかけについて教えて頂けますか?
水口弁護士(以下 水口):私は学生~20代の頃 バンドやDJをしたりしていて、弁護士になってから、今もですけど日常的にクラブやライブハウス等に通ってまして、そんな中で段々とアーティストの友達が増えていったんですね、
それで彼らから法律的なこと等の相談を受ける様になって、それがクチコミでどんどん広がっていって、色んな方の相談を受ける様になったんです。それが設立のきっかけでしょうか。
相談を受けていく中で気がついたことは、アーティストは契約や法律について何も知らないことが多いということです。
ーー確かに。ミュージシャンやアーティストは自分の活動=クリエイティブな事については把握しているけれど、それに付随する事については知らなかったり、理解していないことが多いですね。
水口:そうですね。アーティストが契約や法律について学ぶ機会は多くないようです。
そのため、例えばレコード会社やプロダクションと契約するにしても、情報の非対称性がある場合があります。
また、何か困った事が起こった時に、それが法律の問題なのかどうか、弁護士の所に行くべきなのか、区役所や市役所に行くべきなのか、警察に行くべきなのか、わからない人も多いわけです。その切り分けさえ難しい。
ーー問題に直面している本人でもありますし、一般的なトラブルとは異なる問題の事もあるでしょうし。プロダクション等に所属していれば、周りのスタッフに知識があったり、相談先を判断出来たり、対処してくれたりする事もありますが、インディで活動している人たちには、そう言ったサポートが無い場合もありますしね。
水口:そうなんです。仮に問題が切り分けられたとして、弁護士の所に行くべきだと分かったとしても、今度はどの弁護士のところに行けば良いんですか?ってなりますよね。
音楽や音楽業界の仕組みについて何も知らない弁護士に相談しても、話が全く通じなかったりするわけです。
例えば、「(既存楽曲から)サンプリングをしたいんですけど」って言ってみたところで、「サンプリングって何ですか?」ってところから話が始まってしまうと、疑問の解決には到底辿りつかないなんて事も起きるわけです。
Law and Theoryのメンバーは、プロのミュージシャンではないので知識量はプロの人達よりは浅いかもしれませんが、音楽好きが集まっているので少なくとも最低限の共通言語は持っている。
そういう場や窓口があった方がアーティストの方々にとっても良いかなと思って、Law and Theoryを立ち上げました。
ーーなるほど。ありがとうございます。次はちょっと個人的な事を伺いたいんですが、水口さんは学生時代にバンドをやってらしたとの事ですが、どんなバンドだったんでしょう?また現在もクラブやライブハウスに行かれているそうですが、どんな音楽を最近は聴いてらっしゃいますか?
水口:私が中学生・高校生ぐらいの時が、ちょうど90年代後半 日本のメロコア・シーンのブレイク前夜的な時期で、その時に Hi-STANDARD やその周辺のバンドに熱中したのが原体験ですね。
で、そう言うバンドで一番目立つポジションがベース / ボーカルだったんで、ベースを買ってバンドをやり始めたという感じですね。
現在も、もちろんそういったバンドも好きですが、ここ数年はJazzピアニストの ロバート・グラスパー(Robert Glasper) 周辺のシーンにハマっていて、Jazzピアノのレッスンに通ったりしています。
ーーLaw and Theoryのメンバーの方々も、ハードロック・メタル好きの方がいらっしゃったり、HipHop好きの方や、パンク、レゲエ、ジャズ、南米音楽が好きな方など、本当に多様ですよね。楽器を弾かれる方も多いですし。
ハマったバンドがHi-STANDARDと言うのも、彼らは自分達のレーベルでリリースする等 インディで活躍する日本のバンドの代表格でもありますから、Law and Theoryの活動に通じる何かを感じさせます。
ーーところで、Law and Theoryを2018年に立ち上げてから、今年で7年。具体的な相談内容はお話出来ないでしょうが、例えばアーティストの方から相談される内容の傾向とか、どの様な内容を相談される事が多いとかはありますか?
水口:まず1つ目が制作段階での相談。先ほど例にあげたサンプリングはもちろん、何人かで共作した時の権利関係ですとか、原盤や実演家の権利関係、MVやジャケット・デザイン等、著作権法上の権利関係やそれに付随するものについての相談ですね。
次に活動に関する事。例えばライブやコンサート、コロナ禍の時にはライブ中止とか報酬未払いなどの相談が非常に多かったです。あとは楽曲を提供する時の権利処理などですかね。
その後に来るのが契約関係、音楽出版社との著作権契約、プロダクションとのマネージメント契約、レコード会社との実演家契約など。いわゆる伝統的な音楽業界の仕組みに関する相談関係。
または、伝統的な音楽業界の仕組みとは異なる形で活動している方、TuneCore Japan等のディストリビューターを使って配信等をしているインディペンデントなアーティストや小規模なマネージメントチームからの相談もあります。
ーー伝統的な音楽業界の仕組みとは、いわゆる「今までの音楽業界の仕組み」つまりプロダクションに所属して、メジャーなレコード会社と契約してと言った既存のシステムと言うことですね。
水口:そうです。それから、各種権利団体との契約ってかなり複雑なので、そう言った所との契約や手続きの相談等もありますし、他人の曲を使用するパターン、配信関係とか、カバーする時なとの権利関係の相談もありますね。
TuneCore Japanさんで2020年から8回に渡って「アーティストのための法と理論」を連載させてもらったり、2022年からシーズン2として、現在も連載中の「アーティストのための法と理論 ビギナークラス」をさせてもらっているおかげで、アーティストの方々からの相談も、割と法律を理解された上でお問合せを頂く事が多くなってきてはいます。
ーーなるほど。アーティストが自身の活動に関連する法律を学ぶ機会の提供、そして相談窓口としての役割と言った、水口さんがLaw and Theoryを設立された当初「必要だ」と感じられた事は、この7年間の活動で どんどん広がっている感じですね。
今回はお話を伺う貴重な機会を頂き、誠にありがとうございました。
最後に
文化庁では、文化芸術の担い手である芸術家等が契約内容を十分に理解した上で安心・安全な環境で業務に従事できるよう、外部有識者による「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」を2021年9月から開催。
2022年7月には「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」を公表しています。
2024年11月には、音楽事業者のみならず様々な分野で活動をするフリーランス事業者を対象とした「フリーランス・事業者間取引適正化等法」も施行されました。
今までの仕事の仕組み=既存の枠組み以外の形で活動をする人々は、ミュージシャンやアーティストに限らず増えてきています。
一方で、デジタルツールの発展などもあり、著作者の権利を侵害するトラブルなども増えています。
必要な情報を得て、知識を学び、相談窓口を確保する事は、自分達の活動や作品を守るためにも大切なことだと思います。
その為にも まだの方は、ぜひ「音楽系フリーランスのための契約ガイド」のアーカイブ動画やガイドブックをチェック。
法律関係でお悩みがある方は、THE MAGAZINEに掲載中の アーティストのための法と理論 にて該当する記事がないかを見てみたり、Law and Theoryさんにご相談なさってみてください。
- 記事内紹介+関連リンク
- 公益社団法人 著作権情報センター(CRIC)Website音楽系フリーランスのための契約ガイド
- THE MAGAZINE アーティストのための法と理論 記事一覧
- 音楽家のための法律相談サービス Law and Theory
- Law and Theory X(Twitter)アカウント @lawandtheory
- 水口瑛介弁護士 X(Twitter)アカウント @eisukeartfct